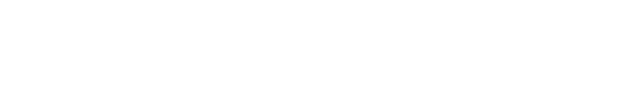膀胱がん
膀胱がんは、膀胱にできるがんで、自覚症状のない血尿が出た際に注意が必要です。早期発見の場合は、内視鏡の手術が可能ですが、進行している場合は、摘出手術が必要になります。
症状:最多は無痛性血尿が85%
膀胱鏡的に同定できる膀胱腫瘍のほとんどすべては、少なくとも顕微鏡的血尿を示すとされます。
血尿は間欠的なことが多く、1-2回の陰性結果では膀胱腫瘍を除外できません。
次いで膀胱刺激症状(頻尿、尿意切迫、排尿困難)が多く、
びまん性上皮内がん(CIS)や浸潤性膀胱がんで見られることが多いですが、
顕微鏡的血尿なしでみられることはほとんどないとされます。
ほかに、尿管閉塞による側腹部痛、下肢浮腫、骨盤内腫瘤があります。
細胞診は高分化癌では限界があり、
高分化がん細胞は細胞学的に正常と似て、また細胞間結合がより強く、尿中に排出されにくいという性質があります。
high gradeや上皮内がん(CIS)ではより高感度ですが、
high gradeでも、20%で偽陰性を呈します。
偽陽性は1-12%で、異型性、炎症、放射線治療(RT)や抗がん剤治療による変性が原因とされ、
治療後数ヶ月からみられることが多く、1年以上持続します。
flow cytometry
細胞の15%以上がaneuploidならがん陽性→high grade、上皮内がん(CIS)で特に正確で、80-90%が同定されます。
尿採取
洗浄液は腫瘍細胞排出を促すため、自排尿より正確に膀胱腫瘍を同定できるとされますが、
剥れた正常移行上皮断片をlow gradeと誤認することで偽陽性が生じます。
長時間の蓄尿で細胞変性が起こるため、早朝第一尿は細胞診には適さないともいわれます。
尿路感染症(UTI)、留置カテ―テル、結石、膀胱内処置も細胞診において構造変性を来たします。
造影剤による浸透圧変化、放射線治療(RT)、膀胱内化学療法、BCG療法も細胞診判定を困難にし、偽陽性を生じます。
自排尿を検体として用いる最大の利点は、膀胱以外の尿路(腎盂、尿管、前立腺部尿道)を検索可能であることです。
low grade乳頭状表在性腫瘍における、細胞診、cytometryでのhigh grade陽性所見は、
他の尿路に膀胱鏡的に不可視の上皮内癌(CIS)が存在することを示唆します。
high gradeでは、経尿道的内視鏡切除(TUR)の数週後の細胞診や再切除で、完全切除を評価します。
CT:血尿患者や内視鏡的に明らかな膀胱腫瘍では全例で施行します。
上部尿路腫瘍、治療決定に影響する他の上部尿路異常を検索し、
膀胱腫瘍による尿管閉塞は、筋層浸潤がんを意味します。
経尿道的内視鏡切除による生検(TUR-biopsy)
部分切除を考慮する時
細胞診がhigh gradeがんの存在を示唆するが、膀胱鏡的に腫瘍がないか
すべての腫瘍がlow grade乳頭状表在性に見えるとき
understagingはhigh grade、中間stageの腫瘍で最も多く起こり、
それらでは33%がunderstaging、10%がoverstagingといわれます。
T2aはT2bと比べ、保存的治療での結果がよいですが、経尿道的内視鏡切除(TUR)のみではこの両者を確実に鑑別できません。
肺転移に対し最も高感度なのは胸CTですが、しばしば小、非石灰化病変を同定し、そのほとんどは肉芽腫とされ、
肺病変の大きさと転移の可能性とには強い相関があり、1cm以上の非石灰化病変の多くは転移であり、
単純x-pは小肉芽腫を同定できず、1cm以上の病変のみ同定できるとされます。
2011年の腎盂・尿管・膀胱癌取扱い規約【第1版】にて、
非乳頭状→結節型に
G1, 2, 3→low grade, high gradeに
膀胱癌の前立腺間質浸潤→T4に、前立腺部尿道や導管浸潤→尿道癌に
総腸骨LNが二次所属LNに、N1:1個の一次LN、N2:2個以上の一次LN、N3:二次所属LN転移 に
変更となっています。
尿路上皮がん(UC)
膀胱がんの90%以上は尿路上皮がん(UC)です。
尿路上皮がん(UC)は上皮化生性が強く、紡錘細胞、扁平細胞、腺癌様成分を含むことがあります。
異なる型の腫瘍が共存することは稀ですが、最も多いのは乳頭状high grade 尿路上皮がん(UC)と上皮内がん(CIS)です。
扁平上皮がん(SCC)も浸潤性尿路上皮がん(UC)にしばしばみられます。
膀胱がんの70%が乳頭状、10%が結節状、20%が混合性といわれます。
tumor grade:腫瘍細胞の異型性の程度に基づきます。
gradeとstageの間には強い相関があり、高、中分化の多くは表在性、低分化の多くは筋層浸潤を有します。
gradeと予後との間には強い相関があり、stageと予後との間にはさらに強い相関があります。
low gradeとhigh gradeは基本的に起源が異なるとされ、
low grade(高、中分化)は9番染色体上の1つ以上の抑制遺伝子の欠如により、
high grade(低分化)はp53異常によるといわれます。
乳頭腫(grade 0)は繊維血管性芯部が正常膀胱粘膜で覆われたもので、
上皮は7層以上なく、組織学的に異常を認めないものです。
筋層浸潤と遠隔転移との間には強い相関があるとされます。
筋層浸潤がんで膀胱全摘を受けた男性患者の40%以上で、前立腺浸潤を有し、
その多くが前立腺部尿道、6%が前立腺部尿道浸潤を伴わない間質浸潤を認めました。
前立腺浸潤の40%が間質浸潤を有し、
完全切除にもかかわらず80%が遠隔転移を生じるとされ、
→術後の抗がん剤治療を考慮すべきと考えられます。(その効果に関する結論は出ていません。)
原発性前立腺がんの合併は25%以上で見られるため→術前のPSAチェック、上昇例では前立腺の完全切除が重要です。
膀胱憩室内腫瘍は上皮から直接膀胱周囲組織へ浸潤(膀胱憩室には筋層がない)しますので、
経尿道的内視鏡切除(TUR)では、切除しないで生検にとどめるべき場合もあります。
単純憩室切除や部分切除が行われることが多いですが、保存的切除では予後が悪いともいわれ、
多発性腫瘍や憩室から離れた高度異形成症例では、保存的切除は賢明ではないと考えられます。
low grade表在性乳頭状がんの5%、high grade表在性がん(CISを含む)の20%が血行性、リンパ性転移を示します。
転移に進展するほとんどすべての例が、転移がみつかる以前に筋層浸潤性再発をきたします。
粘膜固有層内のリンパ管、血管浸潤により、転移は表在性腫瘍で起こる場合もあります。
リンパ性転移はより早期に、血行性転移とは別に起こるとされ、
high grade,再発性、T1の10%以下、T2の40%でリンパ節転移をきたし、
全摘例の10-40%がリンパ節転移陽性(N+)で、その35-70%が限局(腸骨分岐部以下の1-2個)転移で、
その10-35%が膀胱全摘、骨盤リンパ節郭清(PLND)で治癒するともいわれます。
剖検では膀胱がん死症例の25-33%で骨盤リンパ節転移がなかったというj報告があります。
膀胱がんの最も多い転移部位は骨盤リンパ節で、リンパ節転移例の78%でみられます。
膀胱周囲リンパ節16%、閉鎖節74%、外腸骨節65%、内腸骨節、仙骨前25%、
傍所属リンパ節である総腸骨節は20%、ほかに鼠径、傍大動静脈リンパ節があります。
血行性転移では、肝38%、肺36%、骨27%、副腎21%、腸13%
播種では、腹部術創、露出された尿路上皮、経尿道的前立腺切除(TUR-P)後の前立腺床、損傷を受けた尿道への播種でも広がります。
前立腺床への播種は稀ですが、high grade、多発腫瘍で起きるとされます。
同時の経尿道的前立腺切除(TUR-P)で播種のリスクは高くならないという報告もありますが、主にlow grade乳頭状がんの場合です。
新規に診断される膀胱がんの55-60%は高、中分化、表在性(T1以下)、乳頭状尿路上皮がん(UC)で、
その多くが経尿道的内視鏡切除(TUR)後に再発します。
最初の診断時、高分化、表在性であった腫瘍の再発では、生涯を通じて最初の特徴を受け継ぐとされますが、
16-25%はより高いgradeとして再発します。
表在性腫瘍の10%は、最終的に浸潤性、転移性がんに進展します。(最初の腫瘍がgrade1,Taでは稀です)
高分化、表在性腫瘍でも長い癌なし期間(5年以上)後の遅発性、浸潤性再発は珍しくないとされます。
新規膀胱がんの40-45%はhigh gradeで、その半数以上は診断時T2以上といわれます。
表在性でも、high gradeはlow gradeより再発しやすく、浸潤性、転移性となりやすいとされます。
新規膀胱がんの25%はT2以上で、そのほとんどはhigh gradeです。
T2以上の85-92%は最初の診断時にすでに浸潤性であり、
T2以上の30-70%は膀胱の他部位に上皮内がん(CIS)を合併します。
T2以上の50%はすでに潜在的遠隔転移を有するため→局所療法の効果に限界があります。
潜在的転移を有する患者さんのほとんどが、1年以内に臨床的遠隔転移に進展するともいわれます。
転移に進展する症例のほとんどすべてが、同時にまたは先行して筋層浸潤を示します。
転移が所属リンパ節に限局した患者さんの10-35%が、膀胱全摘、骨盤リンパ節郭清(PLND)後に転移発現なしに5年以上生存され、
限局したリンパ節転移だけの症例では、内臓、骨転移例より長い臨床経過を期待でき、
局所的外科療法で治癒するものもありますが、一方で広範なリンパ節転移例では治癒は難しいとされます。
明らかなリンパ節転移や遠隔転移例では、膀胱全摘やfull-dose 放射線治療(RT)等の局所療法の前に全身療法を考慮すべきで、
全身抗がん剤治療が奏効し、限局転移巣の外科切除で癌なしが期待できるまでは膀胱全摘やfull-dose放射線治療(RT)を待つべきとされます。
表在性腫瘍における再発とprogressionの予後因子として、
grade、stage(T1)、上皮内がん(CIS)の存在、
リンパ管浸潤、腫瘍径(10g以上)、異形成の存在、腫瘍形態(乳頭状か充実性)、多発性、再発頻度、が挙げられます。
T1、grade3は、完全な内視鏡的切除と膀胱内BCG療法を施行しても、1/3以上がT2へ進展し、
びまん性上皮内がん(CIS)では、膀胱刺激症状(頻尿、尿意切迫、排尿困難)の存在が重要な予後因子であり、
上皮内がん(CIS)の広がりも重要な予後因子(局所限局CISはびまん性CISより予後良好)とされます。
内視鏡的切除(TUR)時のrandom粘膜生検で異形成や上皮内がん(CIS)が見られれば、20-25%が再発するといわれます。
膀胱尿路上皮がんmicropapillary variantは、悪性度が高く、リンパ節転移をきたしやすいとされます。
腺がん(AC)
原発性膀胱がんの2%以下で、
腸管利用の導管、膀胱拡大術、パウチ、尿管S状結腸吻合にも発生します。
1 原発性膀胱腺がん
膀胱三角部やそれに隣接する側壁を含む膀胱底部、膀胱頂部に発生し、
外反膀胱では腺がんが最も多く、
慢性炎症や刺激に反応して発生します。
住血吸虫症でも発生しますが、扁平上皮がん(SCC)や尿路上皮がん(UC)よりは少なく、
コーヒーがリスクファクターとして報告されています。
消化管腺がんと同様に、印環細胞がん、膠質がんは膀胱でも発生します。
印環細胞がんは膀胱に形成性胃組織炎を発生します。
ほとんどが粘液産生性で、乳頭状-充実性、
ほとんどが低分化、浸潤性で、上皮内がん(CIS)よりも腺性膀胱炎とより強く関連します。
膀胱全摘、骨盤リンパ節郭清(PLND)が最も有効であり、
放射線治療(RT)、抗がん剤治療は、腺がん単独例でも、尿路上皮がん(UC)の腺性上皮化生例でも無効とされます。
診断時にすでに進行していることが多く、予後悪いとされますが、
腺がん(AC)の予後が、尿路上皮がん(UC)のそれと顕著に異なるという証拠はないといわれます。
2 尿膜管腫瘍
腺がん84%(粘液産生型69%、粘液非産生型15%)、扁平上皮がん(SCC) 3%、尿路上皮がん(UC) 3%、肉腫 8%。
尿膜管癌
膀胱外に発生する極めて稀な腫瘍で、全がんの0.01%、膀胱がん全体の0.17-0.34%です。
性比は男性が65%とやや多く、68%が41-70歳です。
尿膜管腔には時に腺性増殖様の細胞集団あり=移行上皮の化生したもので→発がんの母地とされます。
腺がん、特に粘液産生型のものが圧倒的に多いですが、部分的ないし全体が尿路上皮がん(UC)の例も少なくありません。
通常腺がんですが、尿路上皮がん(UC)や扁平上皮がん(SCC)のこともあり、稀に肉腫のこともあります。
分泌された粘液中に少数の腫瘍細胞が浮遊した膠様がんや、不規則に配列した印鑑細胞の集団などがあります。
病理学的診断基準
①腫瘍は膀胱頂部に存在し、膀胱の他の部位に腺性膀胱炎(cystitis glandularis)や濾胞性膀胱炎(cystitis cystica)が共存しない
②正常な尿路上皮との間に明瞭な境界を保ちつつ深部への浸潤傾向が強い
③尿膜管の遺残が認められる
④周囲へ広がりを見せつつ膀胱壁内に分枝増殖する
原発性膀胱がんとの鑑別が困難なことは少なくありません。
腫瘍と隣接する膀胱上皮との間に明瞭な境界があり、腫瘍は正常上皮の下の膀胱壁に存在します。
腫瘍が上皮に浸潤し膀胱内に広がると、原発性膀胱がんと類似します。
膀胱前腔に広がることもあります。
症状は血尿(50-70%)、膀胱刺激症状(40-50%)、疼痛(10-40%)で、
診断に有力な所見とされる粘液尿(尿沈さ中のムチン)の頻度は腺がん症例の1/4以下とされます。
腫瘍の形態は様々で特有の所見はないので、膀胱頂部や前壁に限局性病変を認めるときは常に本症を念頭において検索に当たるべきとされます。
臍から血性、粘液性分泌液を見たり、触知可能な腫瘤として粘液瘤を産生することもあります。
腫瘍の多くは点状石灰化を伴い、膀胱腔内に浸潤した腫瘍は尿中に粘液を分泌します。
MRI矢状断層像は腫瘍と尿膜管との関係を明らかにし、きわめて有用です。
消化管からの転移性腺がんとの鑑別も含め、経尿道的生検は最終的に必須です。
初期には症状が出にくいため発見時にはすでに局所浸潤がんであることが多いです。
局所浸潤傾向が強いので、単なる膀胱部分切除のみではなく、残存尿膜管、近接する腹直筋後葉、腹膜の一部を含めたen bloc な摘除が必要とされます。
膀胱壁内で術前診断より広範に、より深く浸潤しており、膀胱部分切除後の局所再発率は15-50%で、
局所浸潤の傾向が強く、術後再発は膀胱、腹壁、Retzius腔、近接腹膜にみられます。
治療は尿膜管切除を伴う膀胱全摘(小径、高分化尿膜管がんを除いて)で、
放射線治療(RT)、抗がん剤治療は効果が低く、
原発性膀胱腺がんよりさらに予後が悪いとされます。
遠隔転移は晩期になるまでみられませんが、腸骨、鼠径リンパ節、大網、肝、肺、骨に転移します。
3 転移性腺癌
原発は直腸、胃、子宮内膜、乳房、前立腺、卵巣が多く、
膀胱がんの0.26%とされます。
原発性膀胱腺がんは稀なので、純粋な腺がんと診断されれば、他の原発巣を検索すべきです。
扁平上皮がん(SCC)
イギリスでは膀胱癌の1%のみ、アメリカでは3-7%といわれます。
エジプトでは75%以上で、その80%はビルハルツ住血吸虫の慢性感染によるとされ、
ビルハルツ膀胱がんは尿路上皮がん(UC)患者さんより10-20歳若いとされます。
外方増殖性で結節性、カビ状、多くは高分化でリンパ節転移、遠隔転移は少ないといわれます。
非ビルハルツ扁平上皮がん(SCC)は結石、長期カテ―テル留置、慢性尿路感染症(UTI)、膀胱憩室などの慢性刺激により発生します。
麻痺患者さんの80%が膀胱に扁平上皮性変化を来たし、5%が扁平上皮がん(SCC)を発生するといわれ、
喫煙も扁平上皮がん(SCC)発生のリスクを増します。
男女比は強くなく、1.3-1.7:1であり、
診断時進行していることが多く、予後が悪いとされます。
角化細胞を尿中に排出し、細胞診で見つかることもありますが、細胞診には限界があるのも事実です。
組織分化度と予後との関連は、尿路上皮がん(UC)と比べてずっと弱いとされます。
治療
積極的な外科治療が必要で、経尿道的内視鏡切除(TUR)、部分切除、放射線治療(RT)では不十分で膀胱全摘が必要となる場合があります。
抗がん剤治療は扁平上皮がん(SCC)には無効とされ(扁平上皮がん(SCC)単独でも、尿路上皮がん(UC)中に扁平上皮がん(SCC)が混在した場合でも)、
stage別の扁平上皮がん(SCC)の予後は、尿路上皮がん(UC)のそれと類似しているとされます。
尿道再発は扁平上皮がん(SCC)の半数に見られ、膀胱全摘時の尿道摘除はルーチンに行うべきともいわれます。
生物学的特徴
再発性腫瘍が多く、多発性に腫瘍発生をきたしやすいです。
がん原性
- 職業的暴露
アニリン染料(ほとんどが芳香族アミン)
2-ナフチルアミン、ベンチジン、4-アミノビフェニール、クロルナファジン
過去アメリカでは、20%が職業的暴露で、潜伏期間は長い(30-50年)との報告があります。
- 喫煙
喫煙者は非喫煙者の4倍incidenceが高く、両性においてリスクが高いといわれます。
リスクは喫煙本数、喫煙期間、吸入程度に相関し、
以前喫煙者は現在喫煙者に比べ、ややincidenceが低いです。
その基準値までの低下には中止から20年かかり、心血管疾患、肺がんにおける期間よりもずっと長いです。
喫煙における特異的癌原性化学物質は同定されていませんが、
喫煙は尿路上皮においてp53変異数を増加させますが、その部位、型には影響しません。
職業的暴露や喫煙は膀胱がん発生のリスクを増加させますが、特異的な表現型とは相関しません。
- コーヒー:喫煙状態を同じくすれば、コーヒーを飲むことでリスクは増さない、
- 鎮痛剤:フェナセチン(化学構造がアニリン染料と似る)大量投与(10年で5-15kg以上)でリスクが増し、
潜伏期間は膀胱が腎盂より長く、25年とされます。
- 人口甘味料:リスクを増すという証拠はほとんどない
- 慢性膀胱炎
カテ―テル留置、結石による慢性膀胱炎は扁平上皮がん(SCC)のリスクを増し、
長期カテ―テル留置中の麻痺患者さんの2-10%が膀胱がんを発生し、その80%が扁平上皮がん(SCC)との報告があります。
ビルハルツ住血吸虫性膀胱炎は膀胱がん、特に扁平上皮がん(SCC)発生と関連し、
原因を問わず、膀胱炎による膀胱がんは重度で長期の感染と関連します。
- 骨盤内放射線治療(RT)
子宮頚がんに対する放射線治療(RT)患者さんでは、膀胱がん発生のリスクが2-4倍高く、
これらでは、診断時high gradeで局所浸潤型が多いとされます。
- シクロホスファミド
シクロホスファミド(CPM)による治療患者さんでは、膀胱がん発生のリスクが9倍高く、
ほとんどが診断時、筋層浸潤を有します。
シクロホスファミド(CPM)の尿中代謝産物であるacroleinが出血性膀胱炎、膀胱がんの両者の原因とされますが、
出血性膀胱炎の発生は、必ずしも膀胱がん発生に関連しないといわれます。
膀胱がん発生までの潜伏期間は比較的短く、6-13年とされ、
尿路保護剤であるメスナが膀胱がん発生のリスクを減じます。
progression率が高いので、非浸潤性であっても膀胱全摘が望ましい場合があります。
- トリプトファン:内因性代謝産物は、膀胱がん発生に有意に関連しないとされます。
- 遺伝性:疫学的証拠はありません。
疫学的データ
Incidence rate 年間10万人あたり、新たに診断される例数
男性は女性の3倍
男性では、全癌の5.5%、前立腺、肺、大腸に次いで4番目に多い
女性では、全癌の2.3%、8番目
両性において年齢とともに増加
白人男性は黒人男性の2倍、白人女性は黒人女性の1.5倍
prevalence 10万人あたりの総症例数
中高年男性では、前立腺に次いで2番目に多い
mortality rate 年間10万人あたりの死亡発生数
男性では、全癌死の2.6%、5番目
女性では、全癌死の1.4%
男性は女性よりも5年生存率が高い
女性は男性より、50%死亡率が高い
年齢 主に中高年
中央値は、男性69.0歳、女性71.0歳
incidenceは年齢とともに直線的に増加、mortalityも高齢ではより高い
思春期や30歳以下の若年では、高分化でより活性が低い傾向
low gradeで表在性のことが多くより予後がよいが、progressionのリスクは若年、高年で同じ
地域、国
incidenceはUK、USで高く、日本、フィンランドで低い
ハワイでは、白人は日系人の2倍高い
剖検での、偶然発見例はない
前臨床的潜伏期間(肉眼的に確認できる大きさになってから症候性になるまでの期間)が短い
上皮内がん(CIS)
- 膀胱鏡では発赤粘膜のビロード状斑点で、多くは内視鏡的に見えません。
- 組織学的には尿路上皮に限局した低分化の尿路上皮がん(UC)です。
- 初期は無症候性ですが、後期には頻尿、尿意切迫、排尿困難など重度の膀胱刺激症状を示します。
- 原発性とは、膀胱がんの既往がなく、上皮内がん(CIS)以外の腫瘍を伴わないものをいいます。
続発性とは、それ以外のものを指します。
高分化表在性腫瘍患者さんではまれですが、high grade表在がん患者さんでは25%以上で合併し、
high grade筋層浸潤がんの20-75%で合併します。
多発性腫瘍では、より多いとされます。
- 10年以上も筋層浸潤しないでいるものもありますが、多くは早期に浸潤がんに進行し、根治治療にもかかわらず予後が悪いです。
- 顕著な尿路症状を示すものでは、筋層浸潤するまでの期間がより短いです。
- びまん性上皮内がん(CIS)で膀胱全摘を受けた患者さんの20%は、顕微鏡的に筋層浸潤を有します。
- 予後が悪く、腫瘍再発率はより高く、経尿道的内視鏡切除(TUR)のみでは40-83%が筋層浸潤に進展します。
- 上皮内がん(CIS)と深部浸潤性膀胱がんの両者において、p53遺伝子の欠損、変異とその産生蛋白の変化がみられました。
上皮内がん(CIS)は浸潤性膀胱がんの前駆病変ですが、p53異常のないlow grade乳頭状腫瘍の前駆病変ではありません。
- 細胞異型度によりgrade2とgrade3に分類され、
- 上皮内がん(CIS)を構成する細胞間の結合が非常に弱く、膀胱上皮が部分的または全層にわたり剥脱するので、
→慢性膀胱炎や慢性前立腺炎様症状を繰り返し、
前立腺症、尿路感染、神経因性膀胱(NB)、間質性膀胱炎と誤診されることがあります。
→尿中へのがん細胞の剥離が必然的に多く、自然尿細胞診陽性率は極めて高い(80-90%)です。
grade2 上皮内がん(CIS)では比較的小型の異型細胞が出現し、尿細胞診でⅢと判定されることあり注意が必要です。
- 上皮内がん(CIS)が疑われれば、多か所ランダム生検(multiple random biopsy)を施行します。
膀胱三角部周辺が好発部位なので→2,3ヶ所追加採取します。
上皮細胞の剥離傾向が強い場合、上皮がすべて脱落し、denuding cystitisの所見となるため、
→生検では確定診断できず、尿細胞診だけが診断の根拠となることもあります。
- 隆起性病変を有する症例でも、尿細胞診が陽性でhigh gradeと思われる場合は、
→上皮内がん(CIS)合併(続発性)の可能性を考えて多か所ランダム生検(multiple random biopsy)を施行します。
- 治療
アドリアマイシン(ADM)、エピルビシン膀胱内注入療法の有効率は30%で、
最も有効であるBCGの完全完解(CR)率は50-65%です。
放射線治療(RT)、全身化学療法は無効であり、
膀胱全摘なら尿道も摘除します。
- 上皮内がん(CIS)では全尿路がんの可能性があり→全尿路スクリーニングとして膀胱生検+両側腎盂カテ―テル尿細胞診,逆行性腎盂尿管造影検査(RP)が必要となります。
尿細胞診(cyto)陽性のみの場合:まず膀胱洗浄液細胞診+両側腎盂カテ―テル尿細胞診,逆行性腎盂尿管造影検査(RP)→膀胱生検
尿細胞診陽性かつ膀胱上皮内がん(CIS)疑い(発赤等)の場合:膀胱生検と同時に両側腎盂カテ―テル尿細胞診,逆行性腎盂尿管造影検査(RP)
- 単腎の膀胱全摘
若年で腹腔内手術、放射線治療(RT)の既往がなければ回腸導管が一般的ですが、
膀胱が上皮内がん(CIS)なら上部尿路再発の可能性が高いため→術後BCG療法のため尿管皮膚ろうが選択される場合があります。
BCG膀胱内注入療法の副作用のReiter症候群
尿道炎(尿道口から膿分泌)、関節炎(関節痛)、結膜炎(眼脂,充血)を三徴とします。
頻度は0.1%、男女比3:1と男性に多く、微生物感染を契機とした自己免疫疾患とされます。
発症までの施行回数は4-6回、眼症状が関節炎に数日から2週間先行し、関節炎は投与後28日頃に発症します。
関節炎は多発性、非対称性で下肢優位とされます。
BCG膀胱内注入療法中に関節炎症状を認める場合はReiter症候群を考慮し、早期に適切な対処が必要です。
治療:BCG感染症を否定し、注入療法中止のうえ、抗菌薬は無効とされますので、
結膜炎はステロイド点眼で早期に軽快し、
関節炎はNSAIDsが奏功しない場合は、慢性持続性関節炎に移行する可能性があり、速やかにステロイド投与(プレドニン5mg/日)を要します。
BCG再投与はReiter症候群が再発するので不可とされます。
表在性(Ta、T1)の治療
予後良好で、5生率70%、ほとんどは他因死
10-15%は最終的により積極的治療を要する
G1-2、TaはT2に進行することは稀、T1は46%が進行(特にG3)
T1は完全切除と思われても不完全切除の事が多く、40%は6週後の再TURで残存腫瘍あり
RTは腫瘍の再発を予防せず、radiation cystitisの問題もあり、適応とならない
全摘は症状が強く、びまん性で、膀胱注入療法に反応しない切除不能乳頭状腫瘍、CIS以外は不適応
high grade,保存療法抵抗性に全摘-疾患特異5生率80%、ほとんどが全摘時T2以上での癌死
high grade、再発性表在性腫瘍やTisは、全摘を考慮する頃には1/3がupstageし、
upstage症例の半数はT3以上かM1
多発性、再発性、high grade、異型性、CISなど腫瘍再発のリスクが高い例には補助膀胱内化学、免疫療法
存在する表在性腫瘍に対しても施行
CISには第一選択
ADM:50mgを週3回-月1回、CRは半数、PRは1/3
low gradeとhigh grade間の奏効率に差はない
再発予防目的では60-90mgを3週-3ヵ月後毎
CISの治療や腫瘍再発予防において、BCGよりも効果は低い
副作用は化学性膀胱炎で、多くの患者で重度となり、少数では永久的な膀胱攣縮に進展
epirubicin:ADMの偏位体で、アントラサイクリンアナログで、ADMより副作用が少ない
CRは33-59%、18%がprogression
主な効果は、播種予防というより、初期治療時存在した不可視癌に対するもの
化学性膀胱炎は5%以下
BCG:免疫反応に対し刺激効果をもつ、表在癌に対する膀胱注入療法では最も有効
炎症性免疫反応を起こし、免疫機構を通じて抗腫瘍効果を発揮
膀胱に慢性肉芽腫性反応を起こす
腫瘍と露出基底膜に接着し効果を発揮、特にfibronectinとの接着が重要
尿中fibronectinの上昇や接着過程を妨害する状況はBCG接着に不利に影響、効果を減じる
初期の無反応は、宿主免疫能やワクチン効力に原因がある
Tokyo株は40mg
膀胱刺激症状が主な副作用で、抗コリン薬にてある程度軽減される
排尿困難91%、頻尿90%、血尿46%、発熱24%、倦怠感18%、嘔気8%、悪寒8%
肉芽腫性前立腺炎も多く見られ、抗結核療法を要する重度の症状は6%
全身性BCG感染は治療死につながる
治療後48時間以上続き、解熱剤に反応しない発熱は経口イソニアジド、ピリドキシン(vitB6)
より長期、重度の全身症状は、イソニアジド、ピリドキシン、リファンピシン
より重症なら、エタンブトール、サイクロセリンを追加
治療期間は6ヶ月コースが適当
VUR患者に投与しても、合併症は増さない
免疫能低下患者やカテ挿入時損傷を受けた患者には投与すべきでない
心血管系疾患に対して禁忌ではないが、細菌性心内膜炎等に対する抗生剤による予防は必要
①予防的投与: 腫瘍再発の予防に有効-TURのみでの再発率42%→BCG療法で17%に減少
注入療法なし、ADM、MMCで40-80%→BCGでは0-41、大体20%
②残存切除不能乳頭状腫瘍の治療:CRは58%
TUR後早期の注入は重度の合併症を招く
少なくとも2週間(大体3-4週間)待って開始するべき
③CISの治療:CISに最も有用,膀胱刺激症状も消失
1-2年の短期間ではCR72%
より長期間では50%以上が再発するが,再発までの期間は3年以上(ADMでは5ヶ月)
長期成績では奏効率40-89%、2コース(1コース6週)後のCRは54%
CISは乳頭状腫瘍より,第2コースに対する反応が悪い
無反応のCISは無反応の乳頭状腫瘍に比べ、T2に進展する頻度が4倍(63% vs. 16%)
第1コース後もCISが残存する例では、より積極的な治療を強く考慮すべき
第1コースに無反応の乳頭状腫瘍では第2コースを考慮するが、
それにも無反応なら他の治療に移行するべき
無反応のlow grade、乳頭状腫瘍では、他の従来の保存療法が妥当
無反応のhigh grade、乳頭状腫瘍、特に再発性では全摘を考慮すべき
④tumor progressionを遅らせる
10年progression(T2以上への)free率、疾患特異生存率は早期BCG療法で有意に改善
最終的にprogressionした症例でも、早期BCG療法はそのprogressionを遅らせた
表在性癌に対する術後療法
高、中分化表在性腫瘍は内視鏡的完全切除後に50%が再発するが、浸潤性になることは稀
→再発頻度や多発性により、反復TURより膀胱注入療法が適当と考えられるまでは
膀胱注入療法を待つべき
high grade、Tis、T1はprogressionのリスク高く、膀胱注入療法を直ちに開始するべき
→BCGのみがprogressionを遅延、予防し、第一選択剤である
TUR後の表在癌のfollow up
3ヶ月毎の細胞診、膀胱鏡を2年間、6ヶ月毎2年間、以後1年毎
細胞診は膀胱鏡のたびに出すべき
最初のTUR後2年、5年間非再発の表在性腫瘍で、更に再発するのは43%、22%、多くはlow grade、表在性
腎盂尿管癌に進展するのは5%以下で、進展までの期間は中央値70ヶ月
→上部尿路検索は過度の必要はない
VUR、high grade乳頭状、CIS、尿管口に隣接した腫瘍ではその頻度はより高い
BCG膀注後の結核性肉芽腫性前立腺炎:1%の頻度、前立腺生検で診断
尿道CISに対するBCG:カテを引きながら注入し、20分陰茎クランプ
Olympus社製Visera EliteでNarrow Band Image(NBI)を用いたTransurethral resection in saline (TURis)。膀胱内を従来のWhite light image(WLI)、NBIで系統的観察を行い、正常所見を含む多部位粘膜生検を行い、いずれの陽性部位もすべてTURした。NBIの陽性所見の認識は比較的容易でNBIを用いたTURisにより従来のWLIでは認識できなかった癌組織を補足し癌の取り残しを有意に減少させることから術後非再発率の向上が期待できる。
2nd TUR
膀胱癌診療ガイドラインでは、非筋層浸潤癌の高リスク群に対しては2nd TURおよびBCG膀胱内注入療法が推奨されている。Second TURBTは残存癌の切除や、深達度の正確な組織診断を行うことで治療方針を決定する目的で行われる。
High grade pT1膀胱癌に対する2nd TUR症例についての臨床的検討:初回TURBTにてT1以上、またはhigh grade Ta腫瘍と診断された膀胱尿路上皮癌症例に対して、TUR scarとその周囲を切除した。初回TURBTからSecond TURBTまでの期間の中央値は44日(14-73)であった。76%と高率に残存癌を認めた。
局所浸潤性(T2-T4、N0-N2)の治療
- 膀胱温存
癌を根絶し、かつ膀胱機能を維持
UC単独で最小限の浸潤性に適する
- 膀胱再建
膀胱全摘
骨盤内再発率10-20%(根治的RT、根治的ケモ、両者併用で50-70%)
手術死は20%から0.5-1%に減少(ケモ死は2-6%)
尿路変向 ①回腸導管 ②非失禁型皮膚ろう型(Kock、Indiana) ③新膀胱 ④尿管皮膚ろう
病理所見で再発のリスク高ければ術後ケモ
TUR
TURのみで治療されたT2の5生率は40%
予後はよいが、局所再発(反復TURや膀胱内注入療法でcontrolされる)が多い
治療としてのTURは、小径、中分化以下のT2aや、全摘が適応とならない患者さんに限られる
最初のTUR後短期間での積極的再TURが、完全切除のために必要
部分切除
適応は限られた単発T2以上-CIS、再発性多発表在性腫瘍の既往、三角部、頸部浸潤、
腫瘍から1.5-2.0cmのマージンを取れないものは適応外
術前に多所生検で、しっかりマージンを取れること、離れた尿路に重度異形成のないことを確認
尿管口外側の腫瘍では、尿管膀胱新吻合が必要
術前M-VAC(4コース)+部切で、5生率65%、正常膀胱機能54%も、膀胱内再発46%
→部切のみと成績変わらず
膀胱内再発が極めて多いので、厳重な膀胱鏡によるfollow必要
根治的放射線治療
根治的外照射:腫瘍に対しtotal 70Gy 7w (35回)+骨盤内に50Gy
→骨盤内照射がLNメタを抑制できるとは証明されてはいない
浸潤性腫瘍に対するRTで5生率は、T1 35%、T2 a40%、T2b 35%、T3,T4 20%、N1,N2 7%
→gradeはRTに対する反応性とは相関なしも、より低分化ほどstage高く予後悪い
5年膀胱内再発率は50-70%
間欠的RT(+部切や外照射)は5年疾患特異生存率70-80%
中性子は光子と比べ有効ではなく、重度の腸管合併症や治療死をよりきたしやすい
70%は治療中に急性、自制内の合併症-排尿困難、頻尿、下痢をきたす
重度の持続性合併症は10%以下で起こる
最も問題となるのは難治性放射腺性膀胱炎で、姑息的膀胱摘除を要することもある
根治的RTに対する反応が不完全で、救済的膀胱全摘の適応となるのは8-15%のみ
→その5生率は38%、合併症率、手術死率は一時的膀胱全摘と比べやや高いのみ
術前放射線治療+膀胱全摘
術前RT(20Gy/1w-40Gy/4w)は全摘単独と比べほとんど-全く有効ではない
T3-T4のビルハルツ膀胱癌や浸潤性SCCには有効
動注化学療法
放射線感受性、相乗生効果をもつCDDPとADMが最も多く使われる
CDDP+RTで2生率90%、ADM+RTで5生率72% -4wごと4コース
- 集学的治療の一手段
- PS 0~2、T2~3N0M0
- アントラサイクリン系、白金錯化合物(シス、カルボ)
容量依存性で動注療法に適する
RT併用によりradio sensitizerとして作用増強効果
- one shot法
血管カテーテル先端を上臀動脈分岐部より末梢に置き、挿入困難な時は上臀動脈を金属コイルで塞栓
腫瘍支配動脈分布量により、片側あるいは両側より適宜分割して薬剤を注入
- リザーバー法
局麻下に片側鼠径部を切開、大腿動脈を露出、仮性動脈瘤の合併を避けるため穿刺部に
5-0プローリン糸をタバコ縫合して血管カテーテルを挿入
腫瘍の大きさや部位で両側性に栄養血管が認められる時は血流改変術
対側の内腸骨動脈と腫瘍側の上臀動脈を金属コイルで塞栓、1側の内腸骨動脈内に1本のカテ先端を置く
→骨盤内全域に抗癌薬を分布させる
分布範囲を確認のため、術後2~3週間後、99mTc-MAAを用いた血流シンチグラフィ
リザーバーとカテの閉塞防止のためヘパリン3000単位を1~2週ごとに注入
感染を併発した時は早期に交換するか抜去
- 治療効果判定はあくまでも病理学的結果に基づくべき
膀胱温存を考慮するには組織学的にT0を確認してから
動注化学療法終了1ヵ月後に、造影CTと膀胱深層生検または全層針生検
以後3ヶ月ごとに造影CTと深層生検を1年間計5回施行
→この間、腫瘍の残存または再発があれば膀胱全摘術
なければ3~6ヶ月ごとに造影CTと膀胱鏡を1~2年間
以降はエコーと膀胱鏡で少なくとも10年間
- 究極の目的は膀胱温存と非再燃非再発非遠隔転移
局所療法であり、傍所属リンパ節を含めた遠隔転移には無効
- CISに対する治療効果はほとんど認められない
BCG膀注療法の併用が必要
- 抗癌剤の副作用はほとんどないが、合併症として陰茎根部の疼痛、皮膚びらんや潰瘍、萎縮膀胱、
坐骨神経障害、フットドロップ
術前化学療法
局所療法後癌死する浸潤性膀胱癌のほとんどは転移により死亡する
術前ケモの論理は、局所浸潤性腫瘍を縮小させるだけではなく、LN、遠隔転移を根絶する
①微小転移は最初の診断時に存在 ②微小転移はその腫瘍量が最小の時に最もよく治療される
③全摘前のdown-stagingは予後を良好にする ④CDDPはRT感受性に作用
⑤RT前の全身ケモはRTによる血管硬化により起こる薬剤到達量の減少を防ぐ
術前ケモ+積極的TURは、cCR 50%、pCR 25-30%
CTでの残存腫瘍は、30-40%は線維化
cCRの33-40%は全摘で癌あり
術前M-MAC,CMV+全摘、部切は、全摘のみと予後変わらない
周術期M-VAC(術前、術後2コースずつ)はCR50%で、全摘のみと変わらない
外科的完全切除が不可能な局所浸潤癌では適切な標準的治療法
短所は、①合併症により全摘不可能となる ②奏効しなかった例では治療の遅れが転移を助長する
③反応性を誤診することで、特にcCR例では全摘を拒否される
膀胱全摘
男性では、膀胱前立腺全摘+PLND、前立腺部尿道浸潤例では尿道全摘
前立腺浸潤がなければ、尿道再発は5%以下であり、尿道摘除は不必要
女性では、前部骨盤内臓全摘-膀胱尿道、子宮、卵管、卵巣、膣前壁
膣容積は減少するが、ほとんどは術後性交は可能
三角部、頸部浸潤があれば尿道摘除するべき
頸部から2cm以上離れた単発性腫瘍では尿道摘除は不必要
尿管は断端陰性となるまで切除するべき
全尿路に重度異型性やCISが見られる稀な例がある
→全尿路を切除するか、疑わしい断端にもかかわらず尿管腸吻合を進める
神経温存膀胱全摘
尿道温存例ではより勃起能が温存されやすい
勃起能非温存例では海綿体内注入、吸引器具、陰茎プロステ-シス
尿路変向
- 尿管S状結腸吻合
anti-VUR手技は、閉塞、結石形成、電解質異常、高Cl性代謝性アシドーシスを高頻度に起こす
吻合部における結腸腫瘍が、10年以上生存例の10%で起こる
この腺癌は、腸粘膜上の便と尿の混合による発癌性による
- 回腸導管(1950~)
合併症:傍ストーマ皮膚炎、傍ストーマヘルニア、ストーマ狭窄、結石形成、
尿管回腸吻合部狭窄、腎盂腎炎、上部尿路機能低下
放射線性腸炎の患者さんでは、空腸、横行結腸導管を選択
空腸導管:空腸からのNa、Cl喪失による代謝異常のため、施行されることは少ない、高K血症多い
厳重な代謝機能チェックとNa、重炭酸塩の補充が必要
横行結腸導管:anti-VUR手技にはより適しているが、それによる吻合部狭窄の頻度が増す
- 非失禁型導尿型尿路変更
回腸のみ (Kock pouch 1987)、回腸盲腸 (Mainz pouch 1986、Indiana pouch 1987)
合併症:抗失禁弁からの尿漏れ、リザーバー内結石、カテ挿入困難、UTI、パウチ尿管逆流
RT後の患者さんでも安全に施行出来るが、尿漏れ、下痢の頻度は増す
- 新膀胱
Camey(1984):回腸のV型ループ、脱管腔化しないため、夜間、昼間尿失禁が多い
蠕動性収縮による高圧のため、anti-VUR手技は成功しない
脱管腔化回腸、回結腸リザーバー:
Ghoneim(1987)、Marshall(1988)、Kock(1989)、Studer(1989)、Wenderoth(1990)
患者さんはValsalva法と尿道括約筋弛緩により排尿、座位のほうが排尿しやすいことが多い
適切な新膀胱容量は500-800ml
夜間、排尿のために起きなければ、遺尿は稀ではない
容量が大きすぎると、排尿が不完全となり間欠的自己導尿が必要
女性でも、尿道が正常に残されていれば造設可能(1994~)
尿路変向患者では、メソトレキセート(MTX)の再吸収が増す
蓄尿される非失禁型導尿型尿路変更や新膀胱では、より大きな問題
尿道を残す尿路変向ではどのタイプにせよ、術後尿細胞診と尿道鏡での経過観察が重要
膀胱全摘、尿路変向の合併症
合併症率は25%
創感染 10%、腸閉塞 10%、出血、血栓性静脈炎、静脈血栓症、心肺合併症
直腸損傷は4%
損傷が小さく便汚染が最小で、RTの既往がなければ、一期的閉鎖と外括約筋拡張による低腸内圧
で、一期的治癒可能
他の状況では、一時的人工肛門を造設すべき
再手術率は10%、手術死率は1%に減少した
膀胱全摘の成績
pT2:5生率、癌なし生存率は65-82%
pT3:5年癌なし生存率は37-61%
cT2,T3でも、全摘による治癒率はどんな膀胱温存療法よりもかなり良好
pN1-2では、全摘、骨盤リンパ節郭清(PLND)は根治的で、5生率は30%
全摘を施行しても、T2の18-35%は最終的に癌死する
全摘後癌死する例の多くは転移により死亡
局所再発率は、T3-4でも12%以下、T2ではさらに低い、
局所再発率は低く、また局所再発例のほとんどは同時または間もなく転移を来すので、
術前RTが全摘のみに比べ予後を改善しないのは当然
術後化学療法
T3-4、N1-3には術後化学療法
全摘後4w毎4コースの化学療法は再発までの期間を有意に遅延(4.3年)、3年癌なし生存率70%
全摘後再発時に化学療法群では(2.4年)、3年癌なし生存率46%
p T3-4、pN1-2で、術後化学療法は3年非再発生存率58%、全摘のみは13%
術後化学療法の適応はpN1
再発の予測因子
grade、pTは、リンパ節転移の最も重要な予測因子
リンパ節転移と遠隔転移との間には強い相関があるが、リンパ節転移なしでも遠隔転移は起こる
腫瘍関連症候群(高Ca血症,好酸球増多,類白血病反応)は転移癌で起こり予後不良だが、非転移でも発生
非腫瘍性病変
上皮過形成
上皮化生
扁平上皮化生:ほとんどが膀胱頸部や三角部に発生
女性の三角部のものはホルモンの影響による通常の形態
剖検では、女性の50%、男性の10%以下にみられる
細胞異型や過角化のないものは、両性において良性
ブルン細胞巣:前立腺部尿道に見られる正常尿路上皮形態で、剖検で正常膀胱の89%にみられる
嚢胞性膀胱炎:ブルン細胞巣に似るが、その中心に好酸性液化を示し、剖検で正常膀胱の60%にみられる
濾胞性膀胱炎:慢性細菌感染に対する非腫瘍性反応、粘膜下リンパ濾胞からなり、点状黄色粘膜下結節
腺性膀胱炎:嚢胞性膀胱炎に似るが、腺性上皮化生を示し、腺癌の前癌状態、骨盤脂肪腫症に多く見られる
膀胱鏡では乳頭状病変として見られるが、多くは肉眼で見えない
異型(atypical)過形成:上皮過形成に似るが、核の異常を示す
表在性膀胱癌の隣接尿路上皮に異型性があれば、35-40%のリスクで浸潤癌に進展
異形成(dysplasia):正常尿路上皮と上皮内癌(CIS)の中間
軽度、中等度、高度にわけられ、高度異形成とCISの区別は困難
軽度、中等度異形成は厳重な経過観察が必要だが、特に治療は要さない
高度異形成、CISは積極的な治療を要する
内反性乳頭腫:慢性炎症や膀胱出口閉塞による良性増殖性病変、多くは前立腺炎患者の三角部や頸部に発生
乳頭種は膀胱腔内よりもむしろ繊維血管性間質に突出し、正常尿路上皮に覆われる
嚢胞性膀胱炎や扁平上皮化生を含み、肉柱性と腺性の2タイプがある
肉柱性:基底細胞の増殖からなる
腺性:中間細胞から起こる腺性膀胱炎の形態をとり、前腫瘍性病変の可能性がある
膀胱の他の部位に尿路上皮癌(UC)を合併したり、UCの既往を持つ患者に発生することが多い
被覆上皮が正常なため、乳頭状というよりも、小隆起性結節として見える
腎原性腺腫:原始腎集合管に似て、尿路上皮の外傷、感染、放射線治療(RT)に対する上皮化生性反応
核異型や核分裂像はなく、男性に多く、小児にもみられ、排尿困難や頻尿を伴う
中腎性腺癌は腎原性腺腫の悪性版で、筋層浸潤が多く、膀胱全摘の適応
leukoplakia(白板症):正常非角化上皮の角化
著明な角化や乳頭間隆起の下方増殖(表皮肥厚)、細胞異型、異形成を伴う扁平上皮化生
前癌病変、あるいは膀胱の他部位の癌の存在を示唆する病変
20%が扁平上皮癌(SCC)に進展
慢性膀胱炎、膀胱結石、長期カテ留置、住血吸虫症に多くみられる
偽肉腫(術後紡錘細胞結節):下部尿路処置、感染の数ヵ月後に発生する紡錘細胞の反応性増殖
平滑筋肉腫と似ており、悪性と誤診され全摘が行われてきた
マラコプラキア:肉眼的に粘膜の黄色隆起
粘膜固有層にMichaelis-Gutmann小体を入れた大食細胞、リンパ球、形質細胞の集族
非尿路上皮性腫瘍
転移性癌:膀胱はほぼすべての他部位原発巣からの転移を受ける
多い順に、前立腺、卵巣、子宮、肺、乳房、腎、胃、メラノーマ、リンパ腫、白血病
小細胞癌:神経内分泌幹細胞由来、同一腫瘍内にTCC成分と混在することもある
他に正常尿路上皮内の樹状突起細胞由来
神経内分泌マーカー(NSE: neuron-specific enolase)が陽性
通常、生物学的に活性が高く、早期に血管浸潤、筋層浸潤をきたす
膀胱小細胞癌例では、肺や前立腺原発の小細胞癌(膀胱に転移、進展しうる)を検索するべき
他部位の小細胞癌と同様に、ほとんどがCDDPベースのケモに反応するが、
ほぼ全例で、ケモやRTは結局は無効
癌肉腫(Carcinosarcoma):実質性と上皮性両方の悪性成分を含む、悪性度の高い腫瘍
実質成分:通常、軟骨肉腫や骨肉腫、上皮成分:TCCやSCC、AC
稀で、中年男性に好発
初発症状は、無痛性、肉眼的血尿
予後は、積極的治療(膀胱前立腺全摘)でも総じて不良-5生率は20%
RTやケモに抵抗性
- 肉腫様癌(Sarcomatoid carcinoma):著明な紡錘細胞成分を示す
これも浸潤性腫瘍で予後不良だが、本来の癌肉腫と混同してはならない
- 肉腫様炎症反応:
これも癌肉腫と混同されることがあるが、良性疾患であり、本来の癌肉腫との鑑別が重要
偽肉腫様反応のほぼすべては、過去6ヶ月以内に、膀胱の外科的処置や重度感染の既往を持つ患者に発生